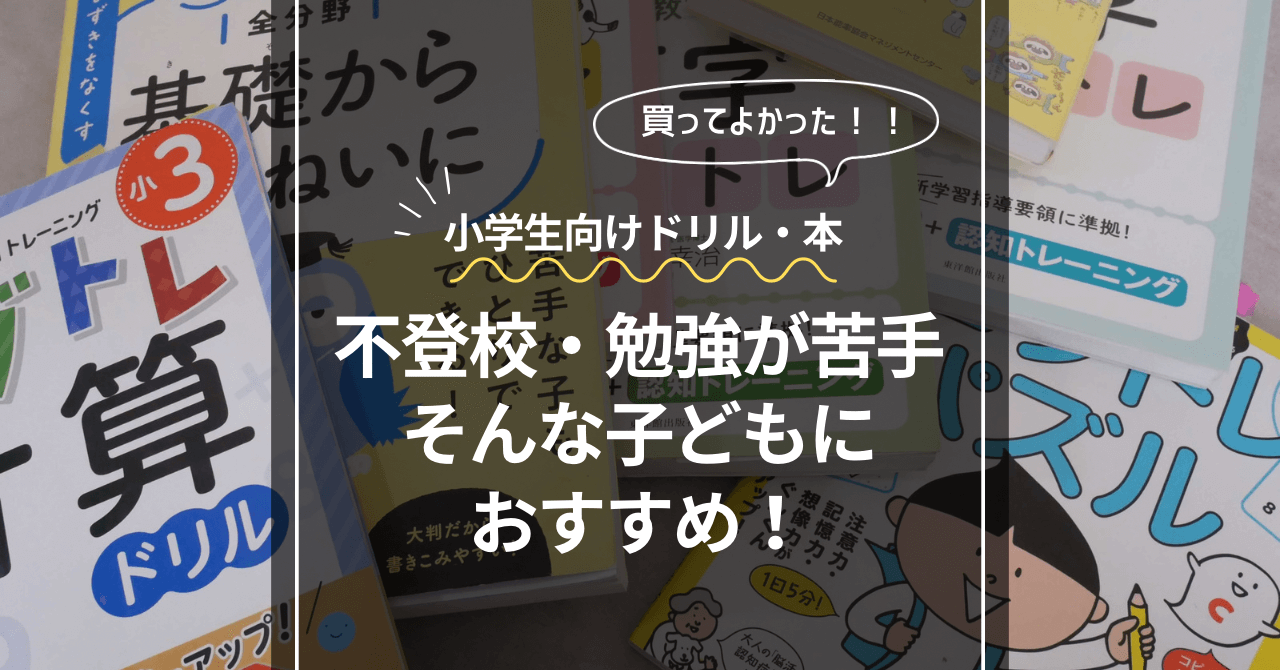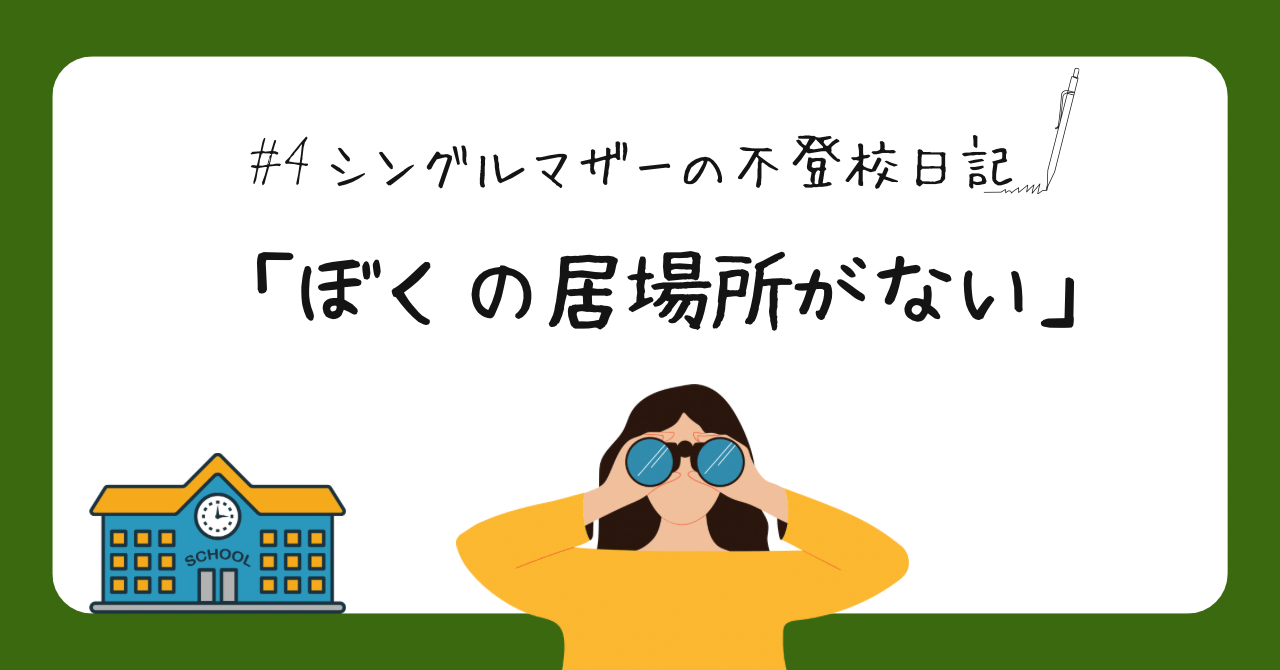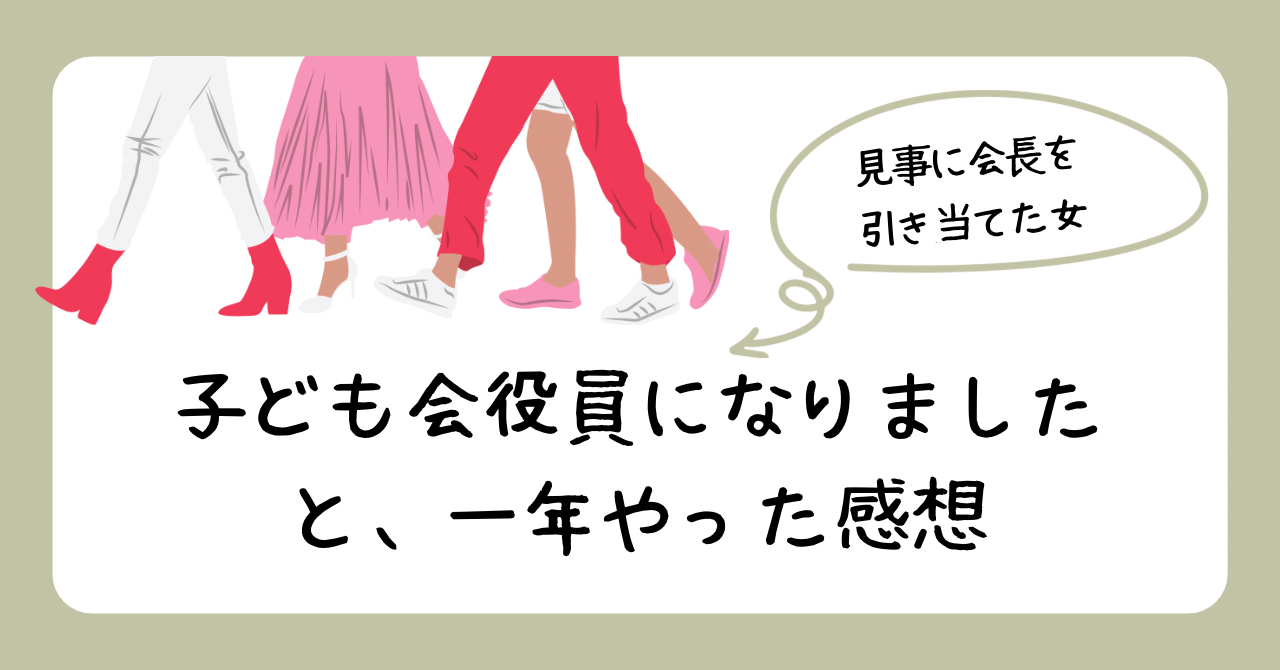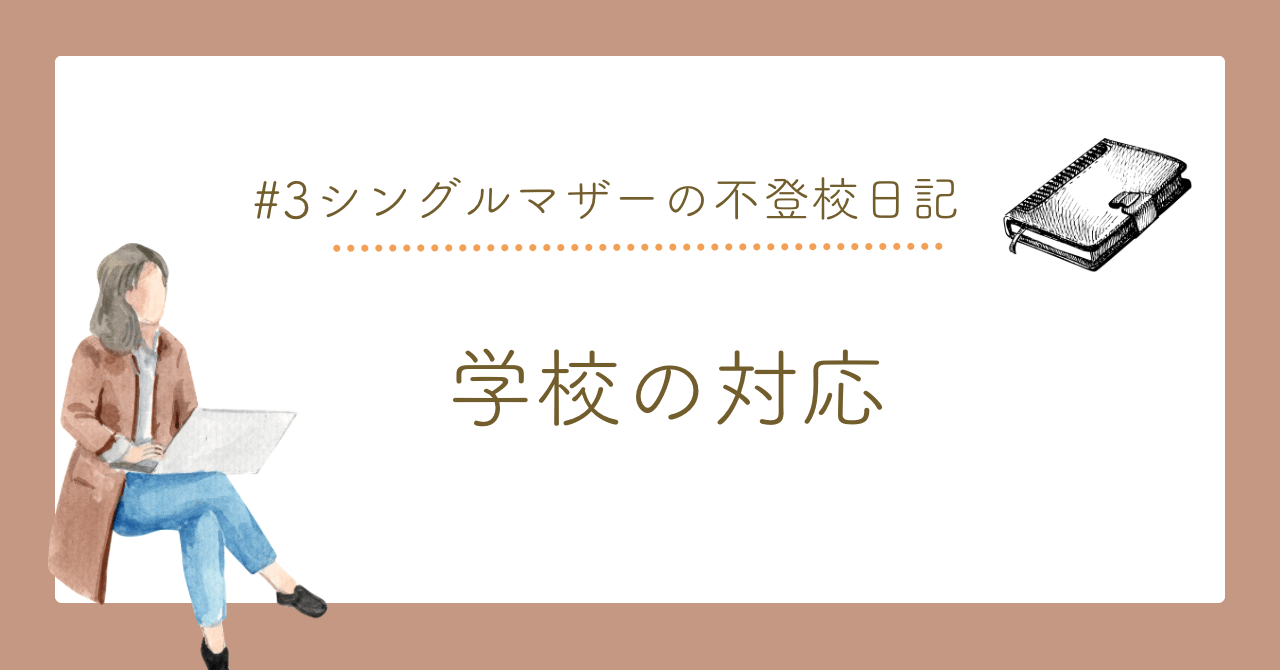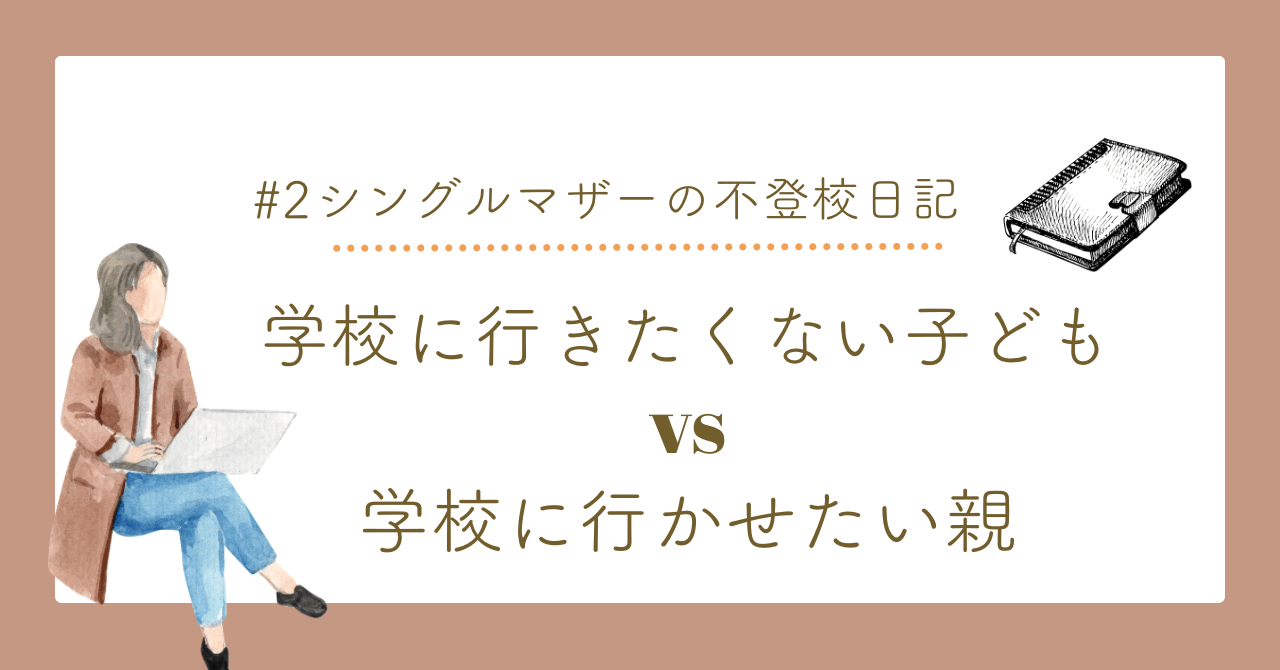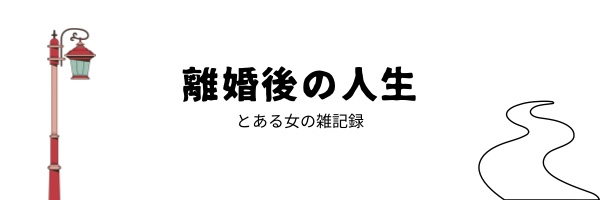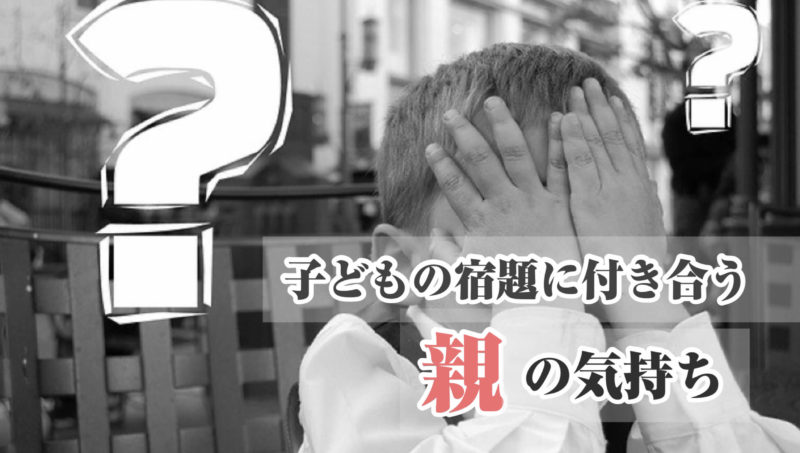こんにちは!Izumiです。
コロナが落ち着いてきて、学校が始まったところも多いのではないでしょうか。
学校が休校になり、子どもの居場所問題や仕事の調整、学習や家事のもろもろ。
一時期は本当にどうしようかと思いました。
そんな中でも一番苦労したのが「子どもの宿題」
親子ともにストレスを抱えながら必死になって取り組みました。。
どうして、子どもの宿題に付き合うことがこんなにも負担に感じるんでしょうか。
子どもの宿題に付き合うことをストレスに感じるのは何故か。
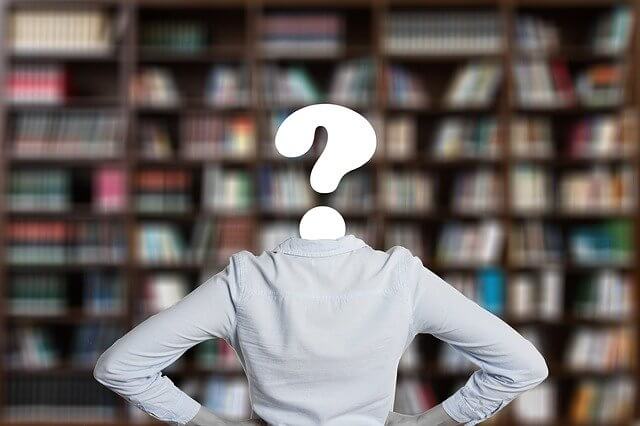
子どもの宿題のことで、大爆発を起こしました。
少し冷静になった頃「何がこんなにも私をストレスに感じさせているのだろう?」と考え始めました。
普段ブログを書く時によく活用するんですが、多くの人がどんなキーワードでネット検索しているか分かるツールがあるですね。
そこで「子ども宿題」と入力すると「子ども宿題しない」とか「子ども宿題怒る」とか「宿題イライラ」とかこういうワードが出てくるわけですよ。
こんなにもストレスに感じているのは私だけでない!ということに気が付き、「ストレスの正体がなんなのか」整理して考えてみようと思いました。
ストレスに感じる理由①親自信に余裕がない

まず一番大きな要因は「親自身に余裕がない」これだと思います。
私の場合を例に取ってみると、
コロナになる以前の生活を思い返してみても時間に追われる日々でした。
仕事、子ども達の迎え、ご飯の支度や家事、子ども達の宿題が終わっていなければ家で付き合う。
平日はとくに時間がないですから早くお風呂に入れだの、歯を磨けだの、もう寝る時間だとせっついて。
そんな生活のどこに子どもの勉強を見る時間があるのだろうか。
市内の小学校と比べても、子ども達の通う学校は宿題の量や給食に関しても厳しめだと思うことはある。
以前ブログにも書いたことがあるけれど、年に2回行われる計算コンク―ルと漢字コンク―ルでは、100点を取るまで毎日行われる。
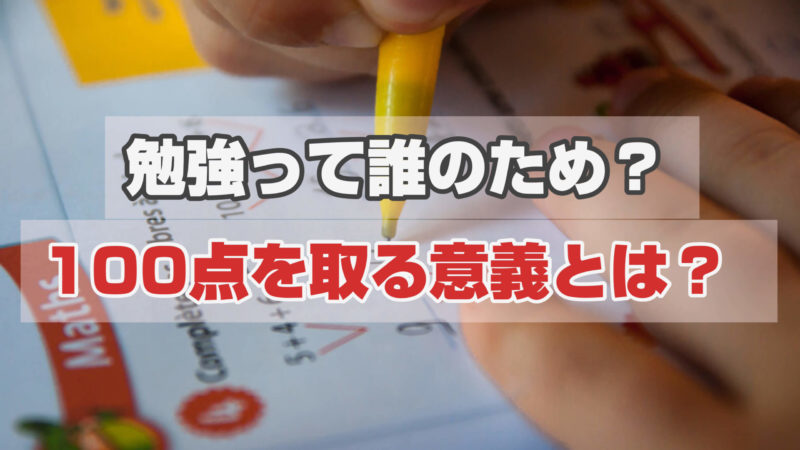
学校の方針はそれぞれあるでしょうから、普段の授業内容や指導の仕方は学校側にお任せとしても、休校になっても同じようなハードさを求められるのは正直困る。
宿題の中には新学年が始まってからやる範囲も含まれており、こういうものは子ども一人では到底無理だ。(だって、まだ習ってないんだもの。)
ということは、親が一緒について勉強を教えなくてはいけない。
休校中の時間割表(1~5時間目)を見た日には、働く親はどうやって時間を捻出すればよいのか?私たち親の時間も皆と等しく1日24時間であることが忘れられてるんじゃないかと思った。
学校側は、子ども達の1日の流れにメリハリがつくように時間割を組んでくれたのかもしれない。市販のドリルも高いですから家計の負担を考え、大量のプリントを刷ってくれたのかもしれない。
しかし余裕のない状態では、そのうようには受け取れなかった。
もう!こんなに毎日一生懸命やってるのに!これ以上私の負担を増やさないでよ!という心の叫びだと思う。
この数か月、仕事は全く進まない。大学の勉強は一切手が回らない。
「あぁ、今日も何も進まなかった…」
日を追うごとにストレス度は強くなっていく。
そういうのも全て横に置いて、子どもの宿題に付き合うおうとした結果、子どもにやる気がない日には親子喧嘩の勃発だ。
ストレスに感じる理由②親子間では遠慮がないから

何故、子どもの宿題を見るとストレスに感じるのか二つ目は「親子だから」
これいつも思うんですけど(我が子の場合)
やりたくない→宿題を始める→投げやりの態度→余計にわからない→怒り出す
もはや始める前からの問題ですね。
そんな子どもの姿を見ながらも、やる気になるようにヒントを出したり。何がわからないのか深堀していく。
しかし子どもは「わからない」の一点張り。
「だーかーらー。何が分らないのか教えてみよ」と言うも、やりたくないが先に来てしまっている状態なので聞く耳持たず。
一生懸命に教えようとしている私からすれば、当然腹立たしいことです。
問題が解けない事はいいのよ。わからないから勉強してるんだから。たださ、分かろうとする姿勢で取り組まなきゃ頭に入ってくるわけないじゃない。
聞く耳塞いだ人に声は届かぬ。
でも、そこで思うは親子間だからできることであること。
もし教室で先生の授業を受けていれば、わからない問題があっても先生に怒ったり、あたったり文句を言うことなどしないはず。
それは子どもであっても立場をわきまえているから。つまりは遠慮があるということ。
- 人様に失礼なことを言ってはいけない。
- 自分の感情をそのままぶつけてはいけない。
そういうことが、分かっているから学校の授業ではそういうことは絶対にしない。
それが相手が親になり、家の中という空間になると家族には気を許していますし、自分の素のままでいられる。さほど遠慮もいらない。
そりゃあ、もう(笑)
全力でイヤだ!という気持ちをぶつけてきますよね。
親からすればたまったもんじゃないですけど、まぁ言いたいことが言える関係性であるのはいいことかもしれない。
ここが親子間で行う家庭学習の難しいところかと思っています。
もちろん世の中には、子どものやる気を引き出し上手いこと教える親御さんも多くいることでしょう。
しかし、私にはそういう器量はないので「まずは態度を改めんかーーーい!」とド・叱られるわけです。。
とはいえ、もしこれが我が子でなかったならば…もう少し優しく、気を長くもって教えられる自信がある。
ということは、やはりそこは私の親としての甘えなのでしょうな。
ストレスに感じる理由③責任があるから

私自身ろくすっぽ勉強などしてこなかったし、いつからか授業は寝てばかりで、テストも名前だけ書いて机に伏せることも多かった。
自分がそんな人間なので、子どもにいい点数もいい成績もとくに求めていません。
それに、本人がやりたいと思ったらいつだって始められる。私が今になって大学に行っているように。
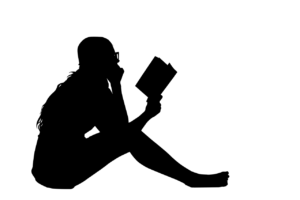
ただ、そうは言いながらも最低限のことはできないと困るわけですよね。
「やりたくない」と言われて「あぁ、そうですか。」なんてことは言ってられない。
上の子はの場合、学習面で遅れがある訳ではないけれど結構拘りの強い部分があって。
(私からすると)少しのことでパニックになったりとか色々あるわけですね。でもそれは彼が繊細であるからだろうし、これは性格ですから。
で、次男は少し成長のスピードがゆっくりだったりする。
そういう部分に対して、自分で度量がないなぁ…といつも反省するんですが。
本当に難しい時があるんです。
でもそれって子ども達の個性ですし、そこを含めて上手いことやっていかなけらばいけない。
そもそも小学生の勉強は基礎ですから、できないと生きていく上で困りますし。学習を通して頑張る心を養ったり、達成感を得る感覚や決められたことを守る練習だったりするじゃないですか。
- 勉強しないとどうなるのか
- テストを白紙で出したらどうなるのか
その結果、自分がどういう立場に追いやられるのか。そういうことがある程度わかる(判断)できる年齢になったら自分で考えて行動すればよい。
ただそれまでは、親がある程度サポートして必要があるとも思っています。
ストレスに感じる理由④子どものことを思うから

子どもの宿題にずっと付き合っていると、なぜこんなにも必死で勉強をするように言っているのか?子どもの宿題なのに、いつの間にか親の方が必死になっていたりして。
子どもも、本当は宿題しないといけないって分かってるはず。
クラスで自分だけ宿題やってなかったら恥ずかしいし、先生に言われるのも嫌だろうし。
それでもやっぱりやりたくない!笑
そうすると、ここで大体2パターンに分かれるように思う。
- 周りの目を気にして、泣きながら無理やり宿題をやる子ども
- 全く気にしない強者
どちらが良いとかはないと思うのだけれど、何にしても結局、困るのは本人なんですよ。
まぁ、こんなことを小学生の子どもに言っても仕方がないかと思いながらも「自分が必要だと思ったらやりなさい」と言う。
きっと、うちの子どもからしたら「そんなのわからんし」みたいな感じなのだろうけど。
それでも、無理やりにでも宿題をする理由は「自分だけ宿題をやってないないのがイヤ」だからなのかもしれないし「先生に注意されるのがイヤ」なのかもしれない。
大人の私からするとそれは違うんじゃないかと思うけれど、今はそういう理由でやるのでもいいのではないかと思うようになった。
恥ずかしい経験をすれば、自分で積極的にやるようになるという考え方も確かにある。
けれど自分の力だけではまだ難しい場合もあるんですよね~。
「だから言ったじゃない!」とお決まりの言葉が出てくるわけですが、大体自分の子どもがどういう性格なのか。その子の特性を分かってますよね。
だから親としてはサポートしていく姿勢でいたいと思う。なるべく困らないように。
そういうのが本当の意味で本人の骨身に染み渡るには、まだしばらくかかりそうね。
【まとめ】子どもの宿題に付き合うことをストレスに感じるのは何故か。

ここまで書いてきて今更感もありますが
専業主婦、兼業主婦ともに経験。今ではシングルマザーである私。
どれも一通り経験してみて思うのは、自分がどの立ち位置にいても大変さ辛さがあるということ。
大体にして、悩みや感じ方というのは人それぞれ違いますから、一概に「私は◯◯だから大変」あなたは「◯◯だから楽」などと言えるものではないなぁと思う。
確かに思い返せば大変だったこともあるけれど、その時々で良いこともあったはずだから。
過去は(いい意味でも、悪い意味でも)自分の都合の良い風に変えられたりしますし。
最近読んだ本の中に、核家族の話が出てきて。
掻い摘んで話すと、昔は沢山の家族で住んでいたからから、子どもの世話をする大人が多かったけれど、それが核家族になってお父さんとお母さんは、絶対に「お父さん役」と「お母さん役」をやらなくてはいけなくなった。というお話。
子どもが生まれた日、もっと言えばお腹に子どもがいると分かった日から「私はお母さんだ」という自覚を持つようになるけれど、実際は訓練を受けたわけでもなく、自分の母親や周りをベースに見様見真似でやるしかない。
確かにそれで何とか私なりにここまで来たわけですけど、まぁ当然として私は未完全なわけです。だから色んなことが上手くいかなくとも、子どものことでストレスを抱えようとも仕方がない。
あまり自分を責めないで、これからも手探りでやっていこうと思う。
辛くなったら吐き出して、やっていきましょう。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました♪